ネガティブを防ぎポジティブを伸ばす!ソーシャルリスニングで磨くVOC戦略

2025.09.24
ブログかつてVOC(Voice of Customer=顧客の声)は、コールセンター対応やアンケート結果が中心でした。しかし現在、顧客の本音はSNS上に多数存在しており、企業の評判や購買行動に大きな影響を与えています。
ポジティブな声をいかに活かし、ネガティブな兆しをいかに早く察知できるかが、CX(顧客体験)の向上や炎上回避の成否を左右する時代です。
そこで注目されるのが「ソーシャルリスニング」です。SNSの投稿をリアルタイムで収集・分析することで、顧客理解を深め、ブランド価値を高める“攻めのVOC活用”が可能になります。
本記事では、ネガティブを防ぎポジティブを伸ばす、ソーシャルリスニングを活用したVOC戦略をご紹介します。
目次
- なぜ今「ソーシャルリスニング×VOC戦略」が求められるのか
- VOC戦略の鍵は“リアルタイム感知”と“定性データの活用”
- Sprinklrで実現するソーシャルVOC活用
- ソーシャルリスニング×VOC戦略で成果を出した企業の事例
- VOC活用を全社戦略にするために
- まとめ
なぜ今「ソーシャルリスニング×VOC戦略」が求められるのか

顧客の声(VOC)はこれまでアンケートやコールセンターが中心でしたが、いまやSNSが大きな情報源となっています。小さな不満が瞬時に拡散し、企業の信頼や売上に影響を及ぼす時代。ソーシャルリスニングを活用し、顧客理解とリスク回避を同時に進めることが重要です。
顧客の声はSNSで知らないうちに広がっている
SNSの普及により、顧客は日常的に商品やサービスへの感想を発信しています。これらの声の多くは企業に直接届くものではなく、第三者同士の口コミや会話の中で広がります。その結果、企業が把握していない「顧客の声」がネット上に大量に存在しているのです。
たとえば、ポジティブな投稿が話題になれば無料の宣伝効果を生み出しますが、ネガティブな体験談が広がればブランド毀損のリスクにつながります。ソーシャルリスニングは、こうした顧客の本音を早期に捉え、施策に反映させるために不可欠な手段です。
小さな不満が拡散され、企業イメージを損なう時代
かつては顧客の不満も数件のクレームとして処理されることがほとんどでした。しかしSNSの時代では、個人の投稿が瞬時に数万人に届き、炎上や不買運動に発展するリスクがあります。特に飲食や小売、サービス業では、接客の小さな不手際が大きなネガティブイメージにつながりやすいのが現実です。
代表的なリスク拡散の流れは以下のとおりです。
| 顧客体験 | 投稿 | 拡散 | 影響 |
| 小さな不満 | SNSに投稿 | シェア・引用で急速拡大 | ブランドイメージ低下、売上減 |
このように、わずかな不満でも「小さな火種」となり、企業にとって大きなダメージにつながる可能性があります。そのため、早期に検知し、迅速に対応することが不可欠です。
定量ではなく「感情・文脈」まで拾えるソーシャルVOCの重要性
従来のVOCは、アンケート結果やクレーム件数など、定量的な指標に偏りがちでした。しかし、実際の顧客心理は「がっかりした」「期待以上だった」といった感情や文脈に表れます。
ソーシャルリスニングでは、投稿文の感情分析やキーワードの共起関係を読み解くことで、数値だけでは見えない顧客体験の質を把握できます。
例えば、同じ「遅い」という声でも、文脈によって改善策は異なります。
- 接客が遅い → 人員体制への不満
- 配送が遅い → 物流・在庫管理の課題
このように、ソーシャルVOCの分析は「言葉の裏側」にある顧客体験の真実を可視化し、CX改善につながる意思決定を可能にします。
VOC戦略の鍵は“リアルタイム感知”と“定性データの活用”
従来のVOCは、コールログやアンケートといった事後的なデータに依存してきました。しかし今の顧客行動はSNSで瞬時に共有され、炎上や拡散リスクも高まっています。VOC戦略を成功させる鍵は「リアルタイムでの感知」と「数値では測れない定性データの活用」にあります。
コールログやアンケート結果からの対応では遅すぎる
コールログやアンケートは長年、VOC収集の主な手段として使われてきました。しかし、これらの方法ではどうしても対応が後手に回ってしまいます。顧客が不満を感じてから回答を集め、分析・施策に反映するまでに時間がかかるため、実際に動き出す頃にはすでに機会損失が発生しているのです。
従来手法の課題
- 回答収集に時間がかかる
- 集計・分析のプロセスが遅い
- 気づいたときにはSNSで拡散済み
例えば、新商品の不評がアンケートで分かる頃には、SNS上で数千件の投稿がすでに広がっているケースもあります。このように、従来型VOCだけではCX改善のスピードが追いつかず、即時に把握できる体制が必要です。
炎上リスクを未然に察知するにはSNS監視が不可欠
ネガティブな口コミは拡散速度が速く、放置すると炎上や不買に発展する可能性があります。SNS監視により、小さな不満の段階で兆候を察知できる体制の構築が重要です。
SNS監視で可能になること
- ブランド名・商品名に関する投稿を常時チェック
- ポジティブ/ネガティブの感情分析
- 拡散の兆しを数値化して早期対策
| 状況 | SNS監視なし | SNS監視あり |
| 不満投稿 | 気づかず拡散 | 即時検知 |
| 企業対応 | 遅れて謝罪・収束長期化 | 初動が早く炎上防止 |
| 結果 | ブランド毀損・売上減少 | 信頼維持・CX改善 |
炎上を消火するのではなく、「芽の段階で摘み取る」ことが、企業のブランド価値と顧客信頼を守るために不可欠です。
定性的なVOCがCX改善のヒントになる理由
数値化されたNPSや満足度調査だけでは、顧客体験の本質を十分に捉えることはできません。SNSに書き込まれる「ちょっと残念」「期待以上だった」といった声こそ、CX改善のヒントになります。
定性的VOCで分かること
- 顧客がどこで期待を裏切られたか
- どんな場面で喜びを感じたか
- 数値に表れない不満・感動の背景
顧客の声と改善ポイントの例
| 顧客の声 | 文脈 | 改善すべきポイント |
| わかりにくい | 操作がわかりにくい | UI/UXやマニュアルの改善 |
| わかりにくい | 説明がわかりにくい | 接客や案内の質の向上 |
| 冷たい | 対応が冷たい | 接客態度や応対マニュアルの見直し |
| 冷たい | サービスが冷たい | 提供プロセスや演出の改善 |
同じ言葉でも文脈によって意味が異なり、対応すべき課題も変わります。表を参考に、顧客の声の裏にある具体的な改善ポイントを見極めることで、CX向上に直結する施策を効率的に立案できます。
Sprinklrで実現するソーシャルVOC活用
Sprinklrを活用すれば、SNS上の顧客の声をリアルタイムで収集・分析し、CX改善や炎上リスク管理に役立てることが可能です。AIによる自動分類や感情分析、ダッシュボードによる可視化で、社内での情報共有もスムーズになり、迅速な意思決定を支援します。
SNS上の膨大な投稿をAIで自動収集・分類
Sprinklrは、Twitter、Instagram、Facebookなど複数SNSの投稿を一括で収集可能です。AIによる自動分類により、ブランド名・商品名・キャンペーンに関連する投稿を整理し、重要な声を見逃しません。
主な機能
- 投稿の自動収集(複数SNS対応)
- キーワードやハッシュタグによる分類
- 不要投稿の除外(スパムや無関係情報)
これにより、従来の手作業による収集・分類の手間を削減し、分析や施策への活用を迅速化できます。
感情分析・ネガポジ判定で“異変”を即時検知
AIによる感情分析で、投稿のポジティブ/ネガティブを自動判定。ネガティブ投稿の急増やブランド評価の異変を即座に把握できます。
活用イメージ
- 急増するネガティブ投稿をリアルタイムで通知
- 投稿の傾向をグラフ化し、トレンドを把握
- 早期対応により炎上リスクを最小化
リアルタイム感知により、問題が大きくなる前に適切な施策を打つことが可能です。
VOCデータをダッシュボードで可視化・共有
収集・分類されたVOCデータは、Sprinklrのダッシュボード上で一目で確認可能です。
ダッシュボードの特徴
- 投稿数・感情割合・トレンドをグラフで表示
- 時系列での変化を追跡
- キャンペーン別や商品別の分析も可能
この可視化により、マーケティング部門だけでなく、経営層や商品開発チームも顧客の声をリアルタイムで把握できます。情報の共有がスムーズになり、迅速な意思決定を支援します。
部署間で共有可能なナレッジ化・タグ分類機能
Sprinklrでは、収集したVOCをタグ付けしてナレッジ化できます。部署ごとに情報を共有できるため、マーケティング、商品開発、カスタマーサポートなど、部門横断で活用可能です。
機能例
- タグ分類(製品カテゴリ、問い合わせ内容、感情など)
- コメントや対応履歴の記録
- チーム間でのナレッジ共有
これにより、顧客の声が組織全体で資産化され、施策の一貫性が保たれます。迅速かつ適切な対応が可能になり、CX改善のスピードが向上します。
Sprinklr>>ソーシャルリスニング×VOC戦略で成果を出した企業の事例
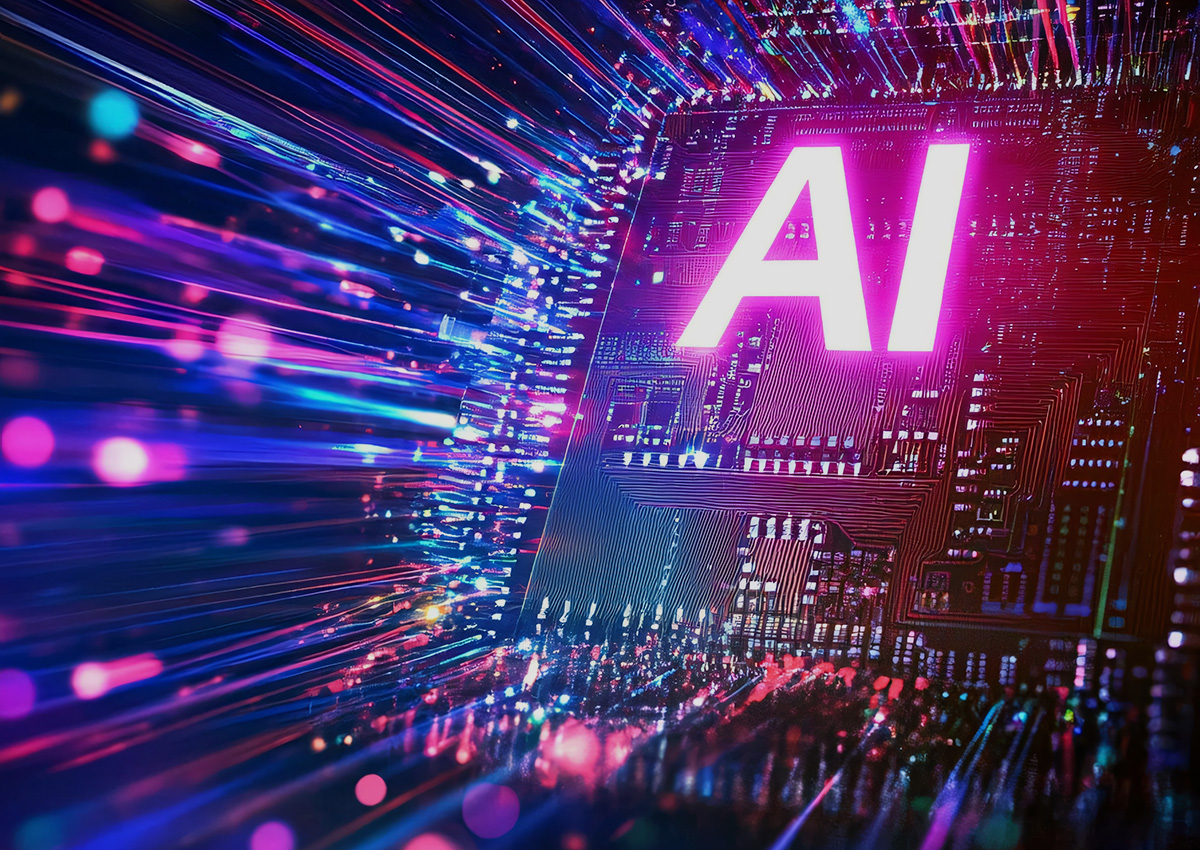
SNS上の顧客の声を活用し、CX改善や商品改良、炎上防止などに成功した企業の具体事例を紹介します。リアルタイムでの声の把握と分析を通じ、迅速かつ戦略的な施策立案が可能になったケースです。
【事例1】新製品の不満をSNSで早期キャッチ → 商品仕様を即改善
ある家電メーカーでは、新製品発売直後にSNS上で「操作が複雑」「説明書がわかりにくい」といった不満が投稿されていました。従来のアンケートでは判明が遅れる内容も、ソーシャルリスニングにより即座に検知できました。
対応内容
- 不満投稿の分析と分類
- 操作マニュアルの改善・動画解説の追加
- 問い合わせ対応マニュアルの更新
結果
- 発売初月の問い合わせ件数が従来製品比で15%減少
- 顧客満足度が向上
- SNSでの不満拡散を防止
この事例では、ネガティブVOCを早期に捉え、迅速に改善策を実施することで、顧客満足度を高めつつCX低下を未然に防ぐことができました。
【事例2】カスハラ傾向を検知 → コンタクトセンターへの共有で対応強化(300文字)
飲食チェーンでは、SNS上で顧客からのクレームや不満が増加傾向にあることを早期に発見。特に従業員への過剰な要求(カスハラ)の兆候をソーシャルリスニングで検知し、情報をコールセンターと現場スタッフに共有しました。
施策内容
- SNS投稿のネガティブ傾向をAIで判定
- コンタクトセンターへのリアルタイム通知
- 対応マニュアル・教育資料の更新
結果
- 従業員の心理的安全性を維持
- 顧客対応の質を向上
- 炎上リスクを低減
この事例では、ソーシャルリスニングでリスク兆候を早期に把握し、部署間で情報共有することで、問題が大きくなる前に対応できました。CX改善だけでなく、従業員の働きやすさにもつながる取り組みです。
【事例3】SNS上のポジティブ投稿を分析 → CX向上施策の材料にして売上UP(300文字)
飲料メーカーでは、新商品の発売後、SNS上のポジティブ投稿を収集・分析。顧客がどのポイントに満足しているかを可視化し、マーケティング施策や販促活動に活用しました。
活用例
- 人気の味やパッケージデザインをキャンペーンに反映
- SNS上で話題になった特徴を広告素材に活用
- 店頭プロモーションの重点ポイントを特定
結果
- 販促施策のターゲティング精度が向上
- 発売初月の売上が従来製品比で10%アップ
- CX向上と売上増加を同時に達成
この事例では、ポジティブVOCを分析することで、顧客が喜ぶポイントを戦略的に活用できました。単なる満足度向上にとどまらず、売上やブランド価値の向上にも直結する成功事例です。
VOC活用を全社戦略にするために
VOCを活用して顧客体験を改善するためには、単なる収集ではなく、分析・施策・改善までを全社で一貫して行う体制が必要です。Sprinklrなどのツールを活用し、VOCを戦略的に経営に組み込む取り組みが求められています。
VOCを「収集→分析→活用→改善」のサイクルに乗せる
VOCを活用するには、単発のデータ収集で終わらせず、次のサイクルで運用することが重要です。
VOCサイクル例
- 収集:コールセンター、アンケート、SNS投稿などのVOCを集める
- 分析:定量データだけでなく、定性・感情・文脈をAIで解析
- 活用:CX改善施策や商品改良、販促施策に反映
- 改善:施策結果を評価し、次のVOC収集・改善につなげる
このサイクルを回すことで、VOCは単なる情報ではなく、戦略的な意思決定の基盤になります。
ソーシャルリスニングを一部門にとどめず、全社で共有できる体制を構築
ソーシャルリスニングをマーケティング部門だけで活用しても、組織全体のCX向上にはつながりません。
全社共有のポイント
- VOCをダッシュボードで可視化し、各部門がリアルタイムで確認可能
- タグ付けやナレッジ化で情報を整理し、部署間で活用
- 商品開発、販促、カスタマーサポートなど、部門横断で施策に反映
全社で情報を共有することで、CX改善のスピードと精度が向上し、顧客視点の施策を組織全体で実現できます。
Sprinklrで“顧客視点の経営”を仕組み化
Sprinklrを活用すると、VOCの収集・分析・活用・改善のサイクルを効率化できます。
Sprinklr活用のメリット
- SNS投稿やアンケートをAIで自動収集・分類
- ネガティブ・ポジティブ投稿をリアルタイムで可視化
- ダッシュボードで部門横断の情報共有
- タグ分類やナレッジ化で改善施策の履歴を蓄積
これにより、VOCは「聞くだけ」の情報ではなく、経営判断や戦略に直結する仕組みとして活用可能です。
まとめ
顧客の“本音”に耳を傾ける企業が、ますます選ばれる時代になりました。従来のVOCは、炎上を防ぐ“守り”の手段にとどまっていましたが、ソーシャルリスニングやSprinklrを活用することで、CXを高める“攻め”の戦略に進化させることができます。VOCは収集するだけでなく、分析・施策・改善まで全社でサイクルを回すことで、顧客視点の経営を仕組み化できます。
弊社では、Sprinklrのシステム提供に加え、導入後の運用サポートも行っております。VOC活用を成功させるための体制づくりや課題解決も支援いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

